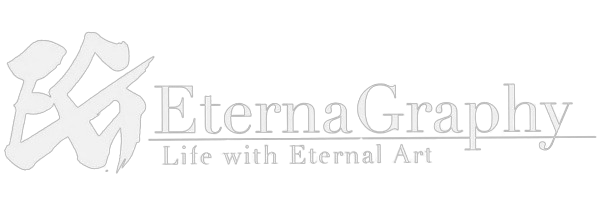書道家光井一輝特別個展『躍動する黎明』を終えて

全ての方々に感謝を込めて
まずはこの個展にお越しいただいた方々、スタジオの方々、その他設営等をお手伝いいただいた方々、
全ての関わってくださった方々に、心よりお礼を申し上げます。
書道家という肩書きで生きていく以上、作品を見ていただくと言う事は、やはり一番嬉しいものです。
しかしその機会は簡単に作れるものではなく、多くの方々のご協力のもとで成り立っていると、毎度強く実感いたします。
たった一つの作品を作る上でも、様々な工程を踏んでいるのと同じく、それを見ていただく上でも、1人の力で容易にできるものではありません。
個展とは、作家にとって数々の工程の融合の上で成り立つものです。
その上で、遠方からお越しいただいた方々、何度も足を運んでいただいた方々、改めてお礼申し上げます。
ここでは少しだけ、個展では語れなかった自分の頭の中をお伝えできればと思います。



守・破・離
「書道家であるなら、綺麗な文字が書けて当然」
これは、6歳から筆を持ち、そこから鍛錬の結果、高校卒業後に書道家の道を選んだ自分の核となる思いである。
守:基本の型を身に付けるまでただひたすらに繰り返す
破:基本の型を忠実に残したまま自分の強みを創る
離:自分の強みから基本を卓越した美しさを見い出す
昨今のSNSの発達により、書道に限らずあらゆるものが、”バズる”をテーマに作られているように感じる。
もちろんそれにより、今まで関わることのなかったものに触れる人の人口は確実に増え、書道もその一つであり、今までどこに行けば書道を見られるのかわからなかった人たちが、無意識にストリーミングで目にするようになった。
新たな時代に広めていくためには、そういった、”バズる”物を創る人たちの存在はとても大切なことである。
しかしそれは逆に、簡単に市場価値を下げる危険なものにもなりうる。
否定をするわけではないが、この『守』の段階を飛び越えて書道家を名乗る人たちが、今は多すぎるように思える。
本来、一作品を作るのに、紙、墨、硯、そして習字教室の頃のように、幾度となく書き上げる書道家、それを美しい作品という形にする額や軸、その全ての段階にそれぞれの職人が関わってくる。
昨今の現状を見た時、本当に今この職人に仕事が流れているであろうか?
本当に書道が広まって良かったと、素直に喜べるであろうか?
自分が有名になるために書道を使って、それによって結果書道が広がっていく事もまた事実であり、そう言った方達には、否定ではなく敬意を示さなければならない。
ただし、それによって、書道が安いもの、たかが文字、そう思われるようなものになってもいけない。
自分はあくまで一書道家ではあるが、常にそう言ったジレンマの中で、それでも次の世代に正しく残していくために、この『守・破・離』の精神は忘れてはならないと考えている。


祈・願・繋・魂
“一見聞こえがいいが、他人の小さな幸せのために自分の幸せを犠牲にすると、人は簡単に孤独になる。そしてその孤独に絶え得る者だけが、表現者として生きていくことができる。”
今回の個展に限らず、書道を必要とする人の心は、ほぼ確実にと言っていいほどこの四つのどれかに帰着する。
いつかこうなりたいという”祈”や、こうなって欲しいという”願”、物事や人の縁起を大切にする”繋”の心、そして、絶対にこうなってやるという強い”魂”。
人間はどこまで行っても人間であり、地位を持ち、富を持ち、名声を持っても、何かを始めた頃の思いは意外と覚えている物である。
部下や社員に話せば説教くさい、暑苦しいと思われるような想いも、向き合って聞けば鮮度高く残っているものだ。
現在の書道家としての立場になるまで、多くの方々のご依頼を受け、その為に多くの想いを聞き、その中で見出した自分なりの答えがこの4文字である。
そう言った思いから、自分の書道のテーマをこの4文字に決め、あらゆる個展やイベントでもこの4文字を掲げてきた。
個展では語れなかった物ではあるが、この4文字にはそう言った人たちの想いが込められている。
一部作品サブタイトル紹介
ここから少し、キャプションに書かなかった作品のサブタイトルを羅列的に紹介する。

『己道』
己の能力に酔いしれ
右も左も決めれる様になった時
己を失わないように

『金龍 -雲ヲ掴ミテ天ヲ舞ウ-』
美しき者は足場をも自ら想像する
(中国の伝説では、龍に羽はなく、空を飛んでるのでは無く口から出すほむら雲を掴んで空を渡り歩くとされている。)

『独』
自分は特別だと立ち向かえることは才能
自分は特別だと逃げないことも才能

『仁』
どれだけ不真面目に生きても味方はできる
どれだけ真面目に生きても敵はできる



人生は絶望より希望が一度だけ多く訪れるように出来てる
今回パフォーマンスでダンスの金光さんとコラボした、書道×音楽のユニット”音ノ葉”。
目が見えなくても耳で感じれる書道、耳が聞こえなくても書を見れば頭の中で流れてくる音楽。
昔は人里離れた旅館などに籠って、酒を片手にただ黙々と製作し、完成作品のみを公開するというスタイルを確立していたが、ある時を境に、出来上がった完成作品より、製作の家庭を見せていくことに価値があると考え始めていた。
そこで考えたのが、パフォーマンスの保存である。
ただ選んだ曲に合わせて書くのではなく、自分の書に合わせ、書のために作った曲に乗せて書く、そしてそれをドローンなどを用いて撮影して映像化することで、人々が興味が湧くような壮大な製作動画を作れると考え、滑走路や温泉村を貸し切って作品を残してきた。
どんなものにも賛も否もある。
しかし、誰もが美しいと思い、圧巻する物を見た時、人はその瞬間だけ、否の感情を忘れる。
陶芸家が目の前で図ったような綺麗な丸のお皿を10枚も20枚も作り始めたら、ケチのつけようがない様なものだ。
自分が作品を作る時、同じく80枚も90枚も書いて作るのは、あくまで届けたいのは、その圧巻性であるからである。
否の意見を忘れた時、その瞬間だけは少し心が平和になる。
すると、その美しさを共有しているその場だけは少し平和になる。
書で世界を、なんて大それた事を言うつもりはないが、自分の磨いてきた技術で、その少し平和な瞬間が、一瞬でも増えればいいと思っている。
“伝統とは、火を灯し続ける事であり、灰を崇拝する事ではない。”
このスタイルでの書道のあり方や、自分の書くものはどこか亜種だと言われるかもしれないが、
それでも自分の書はこれからも、
「見ている間は強くなれる」
「流れている間は平和になれる」
「苦しくて辛くても、眺めていると、あともう一回だけと思える」
そんな作品になっていって欲しい。
音ノ葉にはそんな祈りが込められています。